 352号 雑記
352号 雑記 メンバーの齋藤純二さんに任せきりで、私は参加してないんですが、ツイッター(現・X)もやっております。
●MY DEAR公式ツイッター 「MY DEAR 詩の仲間たち」(担当:齋藤純二)
「MY DEAR 詩の仲間たち」
https://twitter.com/mydear2000s
(リンクが飛ばない場合は、これをコピペして下さい)
●戦後八十年
戦後八十年。ご高齢になるまで、ずっと口を閉ざしてきたこと。戦地で起こった本当の惨状を、ようやく語ってくれた方々の想いに、あらためて耳を傾け、心に刻みつけておきたい。
決して忘れてはならないもの。下記サイトの記録は、日本人の財産と言っていい。ここに、リンクを残しておきたい。
●「戦争証言アーカイブス」●
https://www.nhk.or.jp/archives/sensou/
(リンクが飛ばない場合は、これをコピペして下さい)
★★『 ネットの中の詩人たち 7 』 好評発売中★★
『 ネットの中の詩人たち 7 』 編著:島 秀生
定価(本体1,400円+税) 土曜美術社出版販売
ISBN 978-4-8120-1850-7 C0092
★ 全国の書店、ネットショップから、お取寄せできます。
●三浦志郎さん 既刊詩集。
『海からの言葉』三浦志郎:著 (文芸社)
2017年10月刊
ISBN978-4-286-18737-2 C0093
定価(本体600円+税)
●Kazu.さん 既刊詩集
坂井一則 詩集
『世界で一番不味いスープ』(コールサック社)
2018年 3月刊
ISBN978-4-86435-332-8 C1092
定価(本体1,500円+税)
●くれさん 既刊詩集 初版完売 重版おめでとう!!
木村孝夫 詩集
『私は考える人でありたい』 (しろねこ社:<しろねこ旅の本シリーズ>)
2018年 8月刊 756円
*140文字のツイッターに書いた短い作品66作を収録。
●くれさん 既刊詩集
木村孝夫 詩集
『 六号線 』 ((しろねこ社:<しろねこ旅の本シリーズ>)
―― 140文字と+&の世界 ――
700円+税
●Kazu.さん 既刊詩集
坂井一則 詩集
『 ウロボロスの夢 』(コールサック社)
2019年 11月刊
ISBN978-4-86435-416-5 C1092
定価(本体1,800円+税)
●くれさん、こと、木村孝夫さんが
白鳥省吾賞で優秀賞を受賞されました!!
●くれさんが新詩集を出版!!
木村 孝夫 詩集
『 福島の涙 』(モノクローム・プロジェクト)
2020年6月1日刊
ISBN978-4-88330-020-4 C0092
定価(本体1,200円+税) 販売:らんか社
●くれさん、こと、木村孝夫さんが受賞!!
「第35回国民文化祭・みやざき2020 & 第20回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会」の、
文芸ジャンル、「詩の祭典」への応募において、
木村孝夫さんの作品「原発大地」が、
「第35回国民文化祭宮崎県実行委員会、第20回全国障害者芸術・文化祭実行委員会会長賞」
を、受賞されました。
●三浦志郎さんが新詩集を出版!!
三浦志郎 詩集
『 時の使者 』(文化企画 アオサギ)
2020年 12月刊
ISBN978-4-909980-16-8 C0092
定価(本体1,500円+税)
* amazonから注文できます。
●藍音ななをさんが新詩集を出版!!
藍音ななを 詩集
『 おいしいは愛しい 』(純和屋)
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
●雨 音さんが新詩集を出版!!
雨 音 詩集
『 ドロップス 』(純和屋)
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
*なお、本詩集と、日頃の雨音さんの女性の生き方像が評価され、
★☆★ 祝 祝 ★☆★
雨 音さんが、第二回宮尾節子賞 を受賞されました!!
●青島江里さんが新詩集を出版!!
青島江里 詩集
『 無数の橋 ─ きみへのエール 』 (純和屋)
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
●木村孝夫さん(くれさん)さんが新詩集を出版!!
震災から9年間の名詩ピックアップと、
震災10年目の新作からなる、木村孝夫さん集大成の詩集です。
木村孝夫 詩集
『 言 霊 』 (純和屋)
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
●Kazu.さんが新詩集を出版!!
坂井一則 詩集
『 夢の途中 』(コールサック社)
2021年 11月刊
ISBN978-4-86435-501-8 C0092
定価(本体1,800円+税)
*全国の書店(取り寄せ)や、ネットショップで注文できます
●富士伊真夜さんが新詩集を出版!!
富士伊真夜 詩集
『 長い旅 』 (純和屋)
むしろ心を病みそうになってる人こそ、読んでほしい
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
●くれさんが新詩集を出版!! 3月11日の震災11年目の日に。
木村 孝夫 詩集
『 十年鍋 』(モノクローム・プロジェクト)
2022年3月11日刊
ISBN978-4-88330-027-3 C0092
定価 1,320円(本体1,200円+税) 販売:らんか社
*全国の書店(取り寄せ)や、ネットショップで注文できます
● 綴木 黎さんが新詩集を出版!!
綴木 黎 詩集
『 自転車に乗って 』 (純和屋) ¥800
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
● 澤 一織さんが新詩集を出版!!
澤 一織 詩集
『 春が来て ─ 妊活生活の夫 ─ 』 (純和屋) ¥1000
澤 一織 詩集
『 ヒーローなんていなくてもいい 』 (純和屋) ¥1000
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
● かすみじゅんさんさんが電子書籍の新詩集を出版!!
かすみじゅん 詩集 Kindle電子書籍 シリーズ第2巻
『 追想の彼方 vol.2 』
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVL8MHV2
★☆★ 祝 祝 ★☆★
滝本政博さんが
第3回 秋吉久美子賞 を受賞されました!!
● 夏 生さんが新詩集を出版!!
夏 生 詩集
『 現 在 地 』 (純和屋) ¥1000
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
● 井嶋りゅう さんが新詩集を出版!!
井嶋りゅう 詩集
『 影 』 (文化企画 アオサギ)
2023年6月18日刊
ISBN978-4-909980-42-7 C0092
定価 2,200円(本体2,000円+税)
*Amazon から注文できます
●Kazu.さんが新詩集を出版!!
坂井一則 詩集
『 あなめあなめ 』(コールサック社)
2023年 10月刊
ISBN978-4-86435-587-2 C0092
定価(本体2,000円+税)
*全国の書店(取り寄せ)や、ネットショップで注文できます
● 滝本政博さんが新詩集を出版!!
滝本政博 詩集
『 エンプティチェア 』(土曜美術社出版販売)
2023年 11月刊
ISBN978-4-8120-2814-8 C0092
定価(本体2,000円+税)
*全国の書店(取り寄せ)や、ネットショップで注文できます
● 山雀 ぐりさんが新詩集を出版!!
山雀 ぐり 詩集
『 ミーファとキューブ 』 (純和屋) ¥800
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
● かすみじゅんさんさんが電子書籍の新詩集を出版!!
かすみじゅん 詩集 Kindle電子書籍 シリーズ第3巻
『 追想の彼方 vol.3 』
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CSX8JNST
● 三浦志郎 さんが新詩集を出版!!
三浦志郎 詩集
『 地下に在り 』 (純和屋) ¥1000
*メルカリの「純和屋」もしくは齋藤純二さんにメールして購入して下さい。
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
井嶋りゅうさんが、詩集『影』で、
第34回 日本詩人クラブ新人賞
第37回 福田正夫賞
を、同時受賞されました!!!
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
坂井一則さんが、詩集『あなめあなめ』で、
第64回 中日詩賞奨励賞(後援:中日新聞社)
を、受賞されました!!!
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
富士伊真夜さんが、
『第40回四日市文芸賞』の、一般の部「小説・評論・ドラマ」部門で
「第40回記念審査員特別賞」を
また、『第22回四日市短詩型文学祭』の一般・現代詩部門で
「CTY賞」を
を、同時受賞されました!!!
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
妻咲邦香さんが
「旅」をテーマの文芸&情報誌「たびぽえ」主催の
第2回たびぽえ大賞
を受賞されました!!!
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
荻座利守さんが
第4回川越文芸賞 準賞(詩の部)
を受賞されました!!!
★☆★ 祝 祝 ★☆★
* 快挙!!
くれさん、こと、木村孝夫さんが
第53回壺井繁治賞
を受賞されました!!!
● 編集雑記
◆戦後80年 沖縄慰霊の日
■ 慰霊の日 生きてくれて、良かった 「おばあちゃんの歌」 11歳が詩朗読
沖縄県糸満市の平和祈念公園で23日に営まれた沖縄全戦没者追悼式では、同県豊見城(とみぐすく)市立伊良波小学校6年の城間(しろま)一歩輝(いぶき)さん(11)が平和の詩を朗読した。題は「おばあちゃんの歌」。沖縄戦を生き延びた祖母が、沖縄民謡「艦砲ぬ喰(く)ぇー残(ぬく)さー(艦砲の食べ残し)」を泣きながら歌う姿を目の当たりにし、戦争が心と体に残した深い傷と、つながれた命の大切さに思いをはせた。
母さおりさん(53)によると、祖母の比嘉キヨ子さん(85)は豊見城村(現・豊見城市)の自宅近くの防空壕(ごう)に家族で隠れていたところに手投げ弾を投げ入れられ、左脚に大けがをした。一緒にいた1歳の弟は即死。キヨ子さんは米軍の病院で右脚から左脚に皮膚を移植する手術を受け、一命を取り留めた。
しかし、脚に残った傷痕は、キヨ子さんにとって強いコンプレックスとなった。娘のさおりさんですら、2年前にキヨ子さんが腰を痛めて入院するまで、傷痕を見たことはなかった。今でも自身のことを「傷もの」と言うという。
「艦砲ぬ喰ぇー残さー」の歌詞には、多くの住民が犠牲になった地上戦で「生き残ってしまった」という自嘲的な意味が込められている。歌は1975年にレコード化されて多くの戦争体験者が共感し、沖縄で長く歌い継がれてきた。キヨ子さんは、孫たちの前で涙ながらに歌い終えると「あの戦で死んでおけばよかった」と漏らした。
その言葉に一歩輝さんは強いショックを受けた。一歩輝さんにとって、キヨ子さんは「いつもニコニコしていて優しいところが好き」と感じるおばあちゃん。自宅を訪ねると、優しく迎え入れてくれる。
詩には「『艦砲射撃の食べ残し』と言われても 生きてくれて本当に良かったと思った」とまっすぐな思いをつづった。一歩輝さんは「詩を書いたことで、自分の命がどのようにしてつながれてきたのかを知ることができた」と振り返る。
式では、キヨ子さんが聞かせてくれた歌を自ら節を付けて歌い、詩に紡いだ思いを堂々と伝えた。
朗読者に選ばれた時、キヨ子さんは「『艦砲ぬ喰ぇー残さー』ということがみんなに知られてしまう」と複雑な表情を見せたというが、この日は会場で一歩輝さんを見守り、「上手で落ち着いていた」とほめたたえた。詩の最後で誓ったように「おばあちゃんが繋(つな)いでくれた命を大切にして 一生懸命に生きていく」。
「おばあちゃんの歌」(全文)
豊見城市立伊良波小学校6年
城間一歩輝
毎年、ぼくと弟は慰霊の日に
おばあちゃんの家に行って
仏壇に手を合わせウートートーをする
一年に一度だけ
おばあちゃんが歌う
「空しゅう警報聞こえてきたら
今はぼくたち小さいから
大人の言うことよく聞いて
あわてないで さわがないで 落ち着いて
入って いましょう防空壕(ごう)」
五歳の時に習ったのに
八十年後の今でも覚えている
笑顔で歌っているから
楽しい歌だと思っていた
ぼくは五歳の時に習った歌なんて覚えていない
ビデオの中のぼくはあんなに楽しそうに踊りながら歌っているのに
一年に一度だけ
おばあちゃんが歌う
「うんじゅん わんにん 艦砲ぬ くぇーぬくさー」
泣きながら歌っているから悲しい歌だと分かっていた
歌った後に
「あの戦の時に死んでおけば良かった」
と言うからぼくも泣きたくなった
沖縄戦の激しい艦砲射撃でケガをして生き残った人のことを
「艦砲射撃の食べ残し」
と言うことを知って悲しくなった
おばあちゃんの家族は
戦争が終わっていることも知らず
防空壕に隠れていた
戦車に乗ったアメリカ兵に「デテコイ」と言われたが
戦車でひき殺されると思い出て行かなかった
手榴弾(しゅりゅうだん)を壕の中に投げられ
おばあちゃんは左の太ももに大けがをした
うじがわいて何度も皮がはがれるから
アメリカ軍の病院で
けがをしていない右の太ももの皮をはいで
皮ふ移植をして何とか助かった
でも、大きな傷あとが残った
傷のことを誰にも言えず
先生に叱られても
傷が見える体育着に着替えることが出来ず
学生時代は苦しんでいた
五歳のおばあちゃんが防空壕での歌を歌い
「艦砲射撃の食べ残し」と言われても
生きてくれて本当に良かったと思った
おばあちゃんに
生きていてくれて本当にありがとうと伝えると
両手でぼくのほっぺをさわって
「生き延びたくとぅ ぬちぬ ちるがたん」
生き延びたから 命がつながったんだね
とおばあちゃんが言った
八十年前の戦争で
おばあちゃんは心と体に大きな傷を負った
その傷は何十年経(た)っても消えない
人の命を奪い苦しめる戦争を二度と起こさないように
おばあちゃんから聞いた戦争の話を伝え続けていく
おばあちゃんが繋(つな)いでくれた命を大切にして
一生懸命に生きていく
───── 以上、 毎日新聞 2025.6.24より
■ 沖縄戦「平和の詩」の朗読に選ばれても おばあちゃんは喜ばなかった
沖縄県糸満市の県平和祈念公園で23日に執り行われた沖縄全戦没者追悼式で、今年は豊見城(とみぐすく)市立伊良波小6年の城間一歩輝(いぶき)さん(11)が「平和の詩」を朗読した。
祖母が沖縄戦で受けた苦しみを題材にした詩「おばあちゃんの歌」。でも、おばあちゃんは最初、孫の大役に戸惑いをみせた。
詩を作るきっかけは、ゴールデンウィークに出された学校の宿題だった。沖縄戦を体験した祖母・比嘉キヨ子さん(85)に2度、じっくり話を聞いた。
〈一年に一度だけ/おばあちゃんが歌う/「うんじゅん わんにん 艦砲ぬ くぇーぬくさー」/泣きながら歌っているから悲しい歌だと分かっていた〉
慰霊の日は県内の学校が休みになり、家族で祖母の家に行って先祖を供養するのが恒例だった。キヨ子さんはこの日だけ、ある歌を歌っていた。
あなたもわたしも、艦砲の食い残し――。「艦砲ぬ喰(く)ぇー残(ぬく)さー」という沖縄民謡だ。
キヨ子さんは5歳だった。当時の豊見城村から家族で逃げていた時に米軍の艦砲射撃が激しくなり、赤ん坊を抱えた避難民が目の前で直撃を受けて死んだ。地元に引き返し、壕(ごう)にこもった。
しかし、米軍に手榴弾(しゅりゅうだん)を投げ込まれ、1歳の弟は顔に大けがを負って亡くなった。キヨ子さんは左太ももが裂け、米軍の病院で右の太ももから皮膚を移植して一命を取り留めた。
○ 実の娘にも見せなかった戦争の「傷」
だが、大きな傷痕が残った。
キヨ子さんは、実の娘である一歩輝さんの母・城間さおりさん(53)にも、「汚いから」と傷を見せたことがなかった。傷のある体では結婚もできないと思ったという。
生き残ってしまった後ろめたさと、傷を背負って生きる苦しさ。
「艦砲の食べ残し」は、「鉄の暴風」と例えられる熾烈(しれつ)な沖縄戦を偶然生き延びた人たちの心境を表す言葉だった。
いつも聞き流していた歌の意味を、初めて知った。
キヨ子さんは、「あのときに死んでおけば良かったと何度も思ったよ」と言った。あまりに「死んでおけば」と繰り返すので、一歩輝さんは泣いてしまった。
〈「艦砲射撃の食べ残し」と言われても/生きてくれて本当に良かったと思った〉
○ 嬉しそうではない祖母 「みんなの前で読んでもいい?」
詩は県内のコンクールで受賞し、全国中継される沖縄全戦没者追悼式での「平和の詩」朗読者に決まった。キヨ子さんが隠してきた体と心の傷を、公にしてしまうことになる。
報告した時、キヨ子さんはうれしくはなさそうに見えた。それでも一歩輝さんが「みんなの前で詩を読んでも大丈夫?」と心配すると、こう答えてくれた。
「孫たちが私のように戦争で苦しむより、平和な世の中になってほしいから大丈夫。頑張りなさい」
〈「生き延びたくとぅ ぬちぬ ちるがたん」/生き延びたから 命がつながったんだね/とおばあちゃんが言った〉
本番では、顔を上げて堂々と朗読し、会場からすすり泣く声が聞こえた。一歩輝さんも涙をこらえるため、会場にいるキヨ子さんを見ないようにした。
大役を終え、「おばあちゃんの話を、今のうちにできるだけ聞いて伝えていきたい」。キヨ子さんは「落ち着いて読んで、頑張っていた」と孫をほめた。
レ
───── 以上、 朝日新聞デジタル 2025.6.23より
◆Z復活プロジェクト
■ 整備士が「Z」に記した1ページ 水没した形見がたどり着いたゴール
京都府久御山町にある「日産京都自動車大学校」。
全国に五つある日産系の専門学校で最も規模が大きく、卒業生のほとんどが日産の販売会社の整備士になる。
そんな学校の生徒たちが5月5日、静岡県小山町にあるサーキット「富士スピードウェイ」に1台の車を持ち込んだ。
1978年発売の真っ赤な「フェアレディZ」(S130型)だ。

サーキットでハンドルを握ったのは、同校の指導教員・井上恵太さん(58)。
ある夫婦から譲り受けた水没車のZを、学生たちが復活させるまでの様子を見守ってきた。
当初、ゆっくりした速度でパレードするつもりで会場に来ていた。
ところが当日の朝、学校の広報担当者から「格好良くスピードを出して走る姿をお願いします」と頼まれた。
これまで校内でテスト走行し、走る、止まる、曲がる、といった動きは確認してきたが、サーキットで100キロ以上を出したことはなかった。
広報担当者を助手席に乗せ、思い切ってアクセルを踏み込む。
エンジンの回転数が上がるにつれて雑音が消え、まもなく120キロに達した。
1周約4.5キロのコースを3周し、ピットに入ろうとしたその時。
アクセルを踏み込んでも車が反応しなくなり、コース上で止まってしまった。
牽引(けんいん)されてピットへ戻り、予定していた距離を完走できなかった。
だが、このZは1カ月後に「ゴール」にたどり着くことが決まっている。
もともとの持ち主である、岡山県倉敷市の夫婦のもとへ戻るのだ。
亡くなった息子の形見であるZを、20年も大切に保管してきた夫婦。
2018年7月の西日本豪雨で水没した後、「教材として使ってほしい」と手放していた。
運び込まれたZを、再び走れるように井上さんたちが約4年かけて修理。
夫婦のもとへ返還するまでの整備記録を、これからひもといていく。
○ 夫婦宛てに書いた手紙
スカイラインが好きで、日産の整備士になった井上さん。
販売会社で働いていた31歳の時に、「京都校で教員をしてみないか」と誘いがあった。
数年務めて販売会社に戻ることが多いが、6年目を終えて「学生たちに教えることを仕事にしたい」と希望。
教員歴は、もうすぐ30年になる。
そんな井上さんが、水没したZのことを知ったのは今から6年前。
教材として校内に持ち込まれていたことは認識していたが、直接は関わっていなかった。
聞けば、23歳で亡くなった大学生の愛車だったそうで、両親が20年にわたって大切に保管してきたという。
ところが、西日本豪雨で水没して泥まみれに。

そのZの存在に、復興ボランティアとして夫婦宅に来ていたトヨタ系の専門学校の学生が気づいた。
「いつか、こんなカッコイイ車をいじってみたいな」と、目を輝かせたそうだ。
その姿を見た両親は、学生向けの教材として提供することを決意。
学校に申し入れたところ、「そういう事情であればぜひ日産の学校へ」となり、ここに来たという。
まもなくコロナ下となり、実習の一部もオンライン化されるなど、学生が車に触れる機会が減っていた。
そこで、あのZを活用できないかと考えた。
21年6月、学生向けに「Z復活プロジェクト」をアナウンス。
授業としてではなく、有志による課外活動としてZを復活させようという計画だ。
新入生を対象に呼びかけたところ、予想を上回る35人が手を挙げた。
もちろん、コロナ下で学生が車に触れる機会を増やしたい、という狙いはあった。
だが、それ以上に「何年も使われない状態では、ご両親に対して失礼だ」という気持ちが強かった。
プロジェクトを立ち上げてすぐ、倉敷に住む夫婦に手紙を書いた。
◇
継続的な活用ができておらず、有効活用できずに早2年が経ってしまいました。
コロナ下で先の見えない中、学生さんには少々窮屈な思いをさせてしまっています。
そんな中ではありますが、少しでもより充実した学校生活を送ってもらえたらと、「Z復活プロジェクト」と銘打ち、有志による活動がスタートしました。
これから少しずつではありますが、学生たちが自身の成長に合わせて車両を復元します。
達成感を感じてもらえるようサポートをしていけたらと思っております。
○ 整備は難航したが
復元したZを夫婦に返還することについては、学生たちには言わなかった。
水没車の整備は難しく、年式も古くて換えの部品もないため、復元できるという確証がなかったからだ。
それに今回のプロジェクトは、授業ではなく課外活動だ。
従来の整備とは違って、期限のない中で納得いくまで作業できることが、学生にとってのメリット。
実際、学生たちがああでもないこうでもないと試行錯誤する姿を見ることができた。
車体に取り付けられたパーツをいったんバラして水洗いし、しっかり乾燥させてから使えるかどうかを吟味。
エンジンを分解してみると、中まで泥が入り込み、重要な部品もさびていた。
車好きの井上さんとしては、自らの手で作業してみたい気持ちはあったが、グッとこらえた。
指示は出さず、学生に聞かれたら答える形で、整備を進めた。
とはいえ、古い型の車であり、学生たちはどう整備していいかわからない部分も多い。
そこで、学校の広報担当者経由で日産本社から、当時の「整備要領書」と「配線図」を入手。
整備士向けの公式の取扱説明書とも呼べるもので、とても役立った。
難しいところはいったんそのままにして、直せる部分から整備。
すると、一部については修理も、現行品による代替も、難しいことがわかった。
学校に掛け合って、パーツ取りのために動かないZを2台購入。
卒業生のつてをたどって見つけたこともあり、市場価格より安くで手に入れることができた。
○ 夫婦のもとへ返したかった理由
プロジェクトが始動してからは、倉敷に住む夫婦の自宅を定期的に訪ねて進捗(しんちょく)を報告。
パーツを分解して洗浄したり、ボディーを板金塗装したりといった様子を、写真や動画で説明した。
3年近くが経った24年4月、夫婦を学校に招いて作業を見学してもらった。
コロナ下でのスタートだったこともあり、ようやく実現した見学だった。
「息子が夜な夜なZを触っていたのを思い出します。元気ならこのくらいの孫がいてもおかしくないのにと思うと、涙が出てきました」
亡きオーナーの母がそう話すと、学生が「完成した時にまたご招待します」と話しかけていた。
そして、年が明けた今年1月。
井上さんは夫婦に電話をかけ、こう伝えた。
「復活のめどが立ちましたので、Zをお返しします」
えっ?
だってあの車は差し上げたものですよ。返していただかなくていいんですよ。
そう言われたので、返したい理由を説明した。
「我々は走れるようにするという目標を達成できました。このZはご両親のもとにあるのが一番幸せです。だからお返ししたいんです」
返還は6月ごろになりそうだが、その時にはプロジェクトに関わった学生は卒業している。
そこで、3月に京都校で完成車両報告会を開くことにした。
報告会では、学生たちが夫婦に鍵の模型と、作業中の写真をまとめたアルバムや寄せ書きをプレゼント。
壇上に立った亡きオーナーの母は、こうあいさつした。
◇
井上先生からの報告をもらうたびに、息子が帰ってきたようで。
息子は大学生で死んでしまいましたが、学生のみなさんには未来があります。
この思いを大切にしてくれてありがとうございます。
息子がまた乗ってくれるかなって思います。
本当に感動です。ありがとうございます。
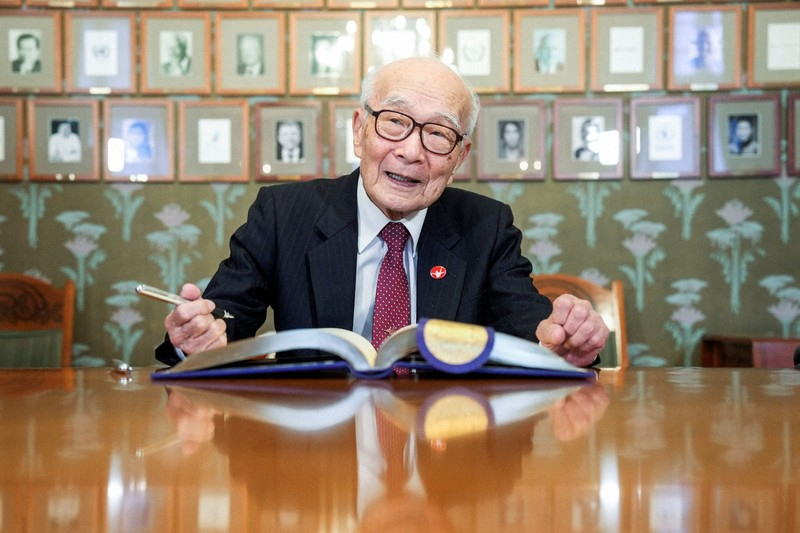
○ 「このZはちゃんとゴールにたどり着いた」
Zを倉敷に持っていく日は、6月上旬を予定している。
それまでに、富士スピードウェイで見つかった不具合を修正すべく、急ピッチで作業中だ。
今回のプロジェクトの目標は、公道を走るために車検を通すことではない。
走る、止まる、曲がるといった基本の動きができて、エンジンがかかることが目標だった。
その目標は、十分に達成できた。
学生たちが「このタイミングで在校していて良かった」と言ってくれた時は、うれしかった。
Zとの別れを惜しむ声も聞こえてくるが、井上さんはそうは思わない。
「このZはちゃんとゴールにたどり着いたんです。いろんな人の思いが詰まったこの車の記録に、自分たちも1ページを記すことができただけで十分です」
───── 以上、 朝日新聞デジタル 2025.6.1より
■ 息子が愛した形見の「Z」、まさかの再会 豪雨で水没し手放したのに
「エンジンの調子が悪いから、しばらくガレージに置いといて」
今から30年ほど前、岡山県倉敷市の実家に帰省していた山本晃司さんは、そう言って赤い車を置いていった。


中古で購入したという、真っ赤な「フェアレディZ」(S130型)。
バイト代をためて買ったもので、これから友人たちと手を入れていくそうだ。
当時、四国で大学生活を送っていたが、駐車場代がもったいないので実家に置きたいという。
試しに助手席に乗せてもらった父・晃さん(82)は「かっこいいけど、乗り心地はイマイチやな」と思った。
高専を卒業後、大学に入り直していた晃司さん。
その理由について、母・富美枝さん(81)には「親のスネをかじりたいから」と言っていた。
「人生で遊べるのは学生時代だけ。留年して30歳くらいまで大学生しようかな」
一方で「雨漏りがしてきたこの家は、いつか俺が建て替えるから」とも言っていた。
「親のスネをかじりながら、家を建て替えるなんて、できるわけないやん」
父も母もそう思っていたが、まさかの形で現実になった。
23歳の若さでバイク事故で亡くなり、両親に保険金を残したのだ。
○ 青信号で交差点を直進中に
1997年11月、高松市にある病院から倉敷の自宅に電話がかかってきた。
「息子さんが事故で運ばれてきたのですが、亡くなられました」
晃さんと富美枝さんが駆けつけると、晃司さんの体は包帯でぐるぐる巻きにされていた。
青信号で交差点を直進していたら、右折してきた対向車にはねられて、全身を強く打ったのだという。
顔はきれいで、まるで眠っているようだった。
バイクで全国各地にツーリングに行っていた晃司さん。
富美枝さんに対して「バイクに乗ったまま死ねたら幸せだな」と言っていた。
中学校の卒業文集では、10年後を想像して書く欄に「バイクを乗りまわす。たぶんどこかで事故って……」と書いていた。
全部冗談だと思っていたのに、本当になるなんて。
しばらく何も手につかなくなった富美枝さん。
晃司さんが亡くなった午後11時8分に合わせて毎晩、自宅近くにある墓に参った。
そして、息子がツーリングで行った北海道を何度も訪れ、足跡をたどった。
晃さんは、ガレージに置かれたままの息子のZを手入れし続けた。
定期的に洗車してワックスをかけ、はずれかかった部品を接着剤やビスで固定。
車内には、晃司さんの写真や愛用していたブーツやリュックなどを並べた。
保険金を使って自宅を建て替え、2階に晃司さんの部屋を作り、ガレージも拡張。
生前、晃司さんが「ガレージはもっと広い方がいいな」と言っていたから。
○ 西日本豪雨で家も車も被害
亡くなって20年近くが経った2018年7月、その自宅が水害に見舞われた。
河川の氾濫(はんらん)や土砂災害などが発生し、230人以上の死者がでた「西日本豪雨」だ。
山本さん宅は、1階の天井近くまで浸水。
2階にある晃司さんの部屋に避難し、自衛隊のボートで救助された。
「晃司が助けてくれたんだ」
命が助かったことはありがたいが、家は泥まみれで、Zも水没。

市内の体育館に避難し、しばらくの間、借り上げ住宅に住んだ。
「晃司が建て替えてくれた家なんだから、俺がなんとかする」
そう言って晃さんは、自ら1階部分をリフォームすることに。
水害の直前に火災保険の特約を外したばかりで、建て替えの資金がない。
そこで、かつて内装関係の会社を経営していた晃さんが、自ら作業することにしたのだ。
床や壁板をはがし、断熱材を取り除いて貼り替える作業。
その作業をボランティアとして手伝ってくれた若者の中に、トヨタ系の自動車整備専門学校の学生がいた。
「いつか、こんなカッコイイ車をいじってみたいな」
ガレージのZを見てそう話すのを聞き、晃さんと富美枝さんは決断した。
「この車は、自動車整備を学ぶ学生さんたちに教材として使ってもらおう」と。
学校に申し入れたところ、「そういう事情であればぜひ日産の学校へ」ということに。
紹介されたのが、京都府久御山町にある「日産京都自動車大学校」だった。
○ 2年後に届いた手紙
Zが運ばれていって2年が経ったが、その後どうなったのかの連絡はなかった。
「きっと、バラバラにされて教材として活用されたんだろうな」
晃さんがそんなことを思っていた21年8月、日産京都自動車大学校の教員から手紙が届いた。
「ご提供いただいたフェアレディZについての報告をさせていただきたいと思い、このようなお便りをお送りしました」
そこに書かれていたのが「Z復活プロジェクト」。
コロナ禍で窮屈な思いをしている学生たちに呼びかけて、有志による課外活動としてZを復活させるという。
「えっ、あの水没して泥まみれになったZを、よみがえらせるの?」
晃さんはその企画に、そして情熱に、胸が熱くなった。
その後、手紙をくれた教員が定期的に倉敷まで来て、進捗(しんちょく)を説明してくれた。
パーツを分解して洗浄したり、ボディーを板金塗装したり。
作業の様子を、写真や動画で見せてくれた。
コロナも落ち着いた24年4月、晃さんと富美枝さんは京都校に招かれて、初めて作業を見学した。
「晃司が夜な夜なZを触っていたのを思い出します。元気ならこのくらいの孫がいてもおかしくないのにと思うと、涙が出てきました」
富美枝さんがそう話すと、学生が「完成した時にまたご招待します」と言ってくれた。
年が明けた今年1月、教員から富美枝さんのスマホに電話がかかってきた。
「復活のめどが立ちましたので、Zをお返しします」
えっ?
だってあの車は差し上げたものですよ。返していただかなくていいんですよ。
そう伝えると、教員はこう言った。
「我々は走れるようにするという目標を達成できました。このZはご両親のもとにあるのが一番幸せです。だからお返ししたいんです」
そして、3月に京都校で完成車両報告会を開いてくれることになった。
返還は梅雨入り前になりそうだが、プロジェクトに関わってきた学生が3月で卒業してしまう。
だから、一足先に報告会を開きたいのだという。
○ 学生たちが同級生のように見えて
完成車両報告会では、学生たちから鍵の模型と、作業中の写真をまとめたアルバムや寄せ書きをプレゼントされた。
富美枝さんは、壇上でこうあいさつした。
◇
先生からの報告をもらうたびに、息子が帰ってきたようで。
息子は大学生で死んでしまいましたが、学生のみなさんには未来があります。
この思いを大切にしてくれてありがとうございます。
息子がまた乗ってくれるかなって思います。
本当に感動です。ありがとうございます。
◇
学生たちと話しながら涙ぐんでいると、「まだ涙は早いですよ」と言われた。
前年4月に訪れた時は、孫のように見えた学生たち。
この日は、車好きだった息子の同級生のように感じられた。
○ 「まるで晃司が乗って帰ってくるようで」
Zが倉敷に戻ってくる日は、6月上旬を予定している。
その日に向けて晃さんは、ガレージに大きな木製のパネルを設置した。
Zが復活するまでの様子や、関わったメンバーを紹介したいと思っている。
富美枝さんは、Zが戻ってくる姿を想像してワクワクしている。
「だって、20年もガレージに眠っていた車が動くんですよ。まるで晃司が乗って帰ってくるようで、待ち遠しくて仕方ないんです」

───── 以上、 朝日新聞デジタル 2025.5.25より
◆SNSひぼう中傷 「発信者情報開示」の申し立てが進む(再録)
■ SNSひぼう中傷受けた医師 投稿者20人超を特定
SNSなどで匿名の投稿者からひぼう中傷を受けたとき、どうすれば被害を回復できるのでしょうか。
メディア出演をきっかけに多数のひぼう中傷を受けた医師は、20人以上の投稿者を特定し、示談や謝罪につなげました。
医師が利用したのは、最近急増している「発信者情報開示命令」の手続き。
数千円程度でできるこの手続きについて、分かりやすく伝えます。(弁護士に頼んだ場合、弁護士費用は別途)
○ 匿名のひぼう中傷 殺害予告まで…
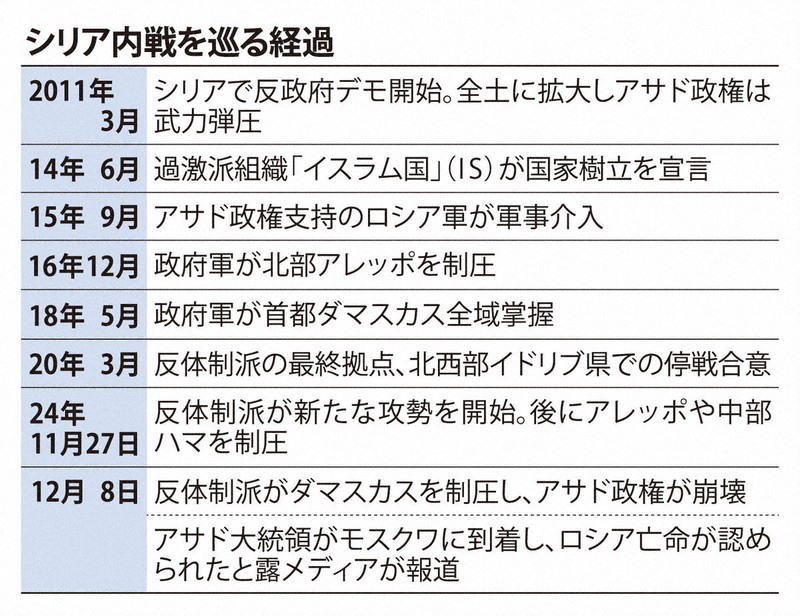
埼玉医科大学総合医療センター教授 岡秀昭医師
ひぼう中傷への“対抗手段”を活用しているのは、感染症が専門で埼玉医科大学総合医療センター教授の岡秀昭医師です。
新型コロナの流行期にメディアの取材に応じ、医療現場の現状や感染予防の重要性を訴えてきました。
その後、毎日のようにひぼう中傷の投稿を受けるようになったと言います。
「聞いたこともない医大のくせに」「ゴキブリ」
容姿をばかにするような投稿は日常茶飯事。SNSに載せていた家族の写真が拡散されることもありました。
また、当時の自宅の住所がさらされ、その住所を見た人から「殺しに行く」と書き込まれたこともあったということです。
岡医師
「家族や仕事への影響が大きかった。黙って無視し、我慢することで収まるケースもあるかもしれませんが、それでは自分の精神が保てませんでした」
○ 岡医師が利用した“発信者情報開示命令”とは

東京地裁
岡医師は弁護士に相談し、「発信者情報開示命令」という司法手続きを利用しました。
この手続きは、ひぼう中傷の投稿を受けた人の情報開示に関する負担を減らそうと、2022年10月に導入されました。
その流れです。

申し立てる先は、地方裁判所です。
認められれば裁判所は▽投稿があったSNSの運営会社などと、▽投稿者が利用する通信事業者に情報の開示を命令します。
情報は例えば、▼IPアドレスや▼電話番号▼氏名▼住所などです。
最高裁判所によりますと、本人が利用した場合の費用は1回あたり数千円程度で、申し立てから開示命令が出るまでの期間は平均で100日程度だということです。弁護士を頼めば費用は別途必要になります。
複数の弁護士によりますと、従来はSNSの運営会社などと通信事業者のそれぞれに手続きが必要だったため、制度の導入により費用や時間は大幅に軽減されたということです。
○ 20人超の投稿者を特定 示談、謝罪につながるケースも
岡医師は、明らかに人格攻撃だと弁護士から判断された40件あまりについて「発信者情報開示命令」を申し立てました。

その結果、20人以上の投稿者を特定し、投稿の削除や和解金の支払いといった示談や和解につなげました。
「バカ」などと投稿していた人からは、「軽い気持ちでひぼう中傷となるような投稿をしてしまった。丁寧なことばで述べるべきで、卑怯だった」などと謝罪する手紙が届きました。
一方、「意見や論評の範囲内だ」と反論する人もいて、民事裁判で争っています。
悪質な投稿者に対しては侮辱罪などで刑事告訴しましたが、投稿者側は無罪を主張し、裁判が続いています。
岡医師は、効果は確実に出ていると感じています。
岡医師
「弁護士との打ち合わせなどで日常生活は制限されましたが、手続きをとったことでひぼう中傷の投稿が減ったことは事実だと思います。投稿者に責任を取ってもらうため、私はしっかりと法的な手段を取りたいと思います」
○ 申し立てが急増 “反撃” 意識が浸透か

最高裁判所によりますと、「発信者情報開示命令」の申し立ては去年1年間の速報値で6779件となり、前年の1.7倍に増加しました。
月別に見ると、

▽制度が始まった2022年の10月は179件でしたが、
▽2023年10月は451件、
▽2024年10月は738件となり、2年間で4倍以上に増えていました。
SNSの問題に詳しい国際大学の山口真一准教授は、増加の背景に人々の意識の変化があると指摘します。

国際大学 山口真一准教授
山口准教授
「著名人などが『法的手続きを取る』と表明する機会も増えている。『反撃をしてもいい』という認識が社会に浸透してきたことで、手続きをとってみようと思う人が増えてきているのではないか」
○ 開示のポイント(1) 投稿を厳選する
では、どうすれば開示が認められるのでしょうか。
岡医師の代理人を務める武中裕貴弁護士は、まずは投稿内容がひぼう中傷に当たるのか、しっかりと吟味することが大事だといいます。
具体的には主に以下のような投稿が開示の対象になるといいます。
▽当事者の社会的評価を下げる
▽容姿などをからかう
▽プライバシーを侵害する
岡医師の場合、「(岡医師が)尊い命を奪った」などの書き込みで開示が認められました。
一方、感染症対策や治療法などに対する批判的な意見は、表現の自由の範囲内だとして申し立ての対象にはしませんでした。
○ 開示のポイント(2) スクショはURL込みで
ひぼう中傷の投稿を見つけた場合、URLが表示された状態でスクリーンショットを撮影しておくことが重要だといいます。
申し立ての際、証拠としての価値に違いが出るからです。
スマートフォンの画面などではURLが写らないケースが多く、パソコンなどで開いた上で、撮影し保存しておくと良いと言います。

武中弁護士
「岡医師からすれば、申し立てた件数よりもひぼう中傷を受けたと感じる投稿は多かったと思います。スクリーンショットで証拠を残した上で、明らかにひぼう中傷と言える一部の投稿に絞って、申し立ての対象にしました」
○ 特定や和解につながらないリスクも
一方、開示命令を申し立てても、被害者が納得するような結論に至らないケースもあると武中弁護士は言います。
▼ケース1
開示命令がでても個人を特定できない。
技術的な理由などにより、SNSの運営会社や通信事業者が個人を特定できる情報を持ち合わせていない場合があるということです。
岡医師の場合も、開示命令が出ても個人を特定できなかったケースが複数ありました。
▼ケース2
投稿者に支払い能力がなく金銭的な補償がされない。
投稿者を特定して慰謝料などを求めても、相手側が支払えず、申し立てにかかった費用を回収できないケースもあるといいます。
武中弁護士
「被害者から相談を受けたときは、投稿者が特定できないリスクがあることを伝えたうえで、『1つだけのアカウントを対象にしても申し立て費用の回収は難しい』と説明しています。司法手続きとしては簡素化され、迅速になっていると思うので、より実効的なものにするにはSNSの運営会社などに対策を促す必要もあるのではないか」
○ ひぼう中傷の投稿減らす取り組みが必要
SNSの問題に詳しい国際大学の山口真一准教授は、「発信者情報開示命令」を活用するのと並行して、ひぼう中傷の投稿自体を減らしていく取り組みが重要になると指摘しています。
山口准教授
「『発信者情報開示命令』の手続きには、ある程度時間や費用がかかる課題がある。しかし、これ以上簡単にすると逆に、ひぼう中傷ではない投稿に対する不適切な申し立てが乱立する可能性もある。今後はむしろ、SNS運営会社が不適切な投稿を素早く削除するような被害防止の取り組みや、投稿者に向けた啓発などが重要になってくる」
───── 以上、 NHK NEWS WEB 2025.5.28より
◆「ロシア兵が足を踏み入れた場所は、われわれのものだ」
この言葉はプーチン氏の本音を表すものです。ロシア(旧ソ連)は第二次世界大戦時における領土拡大にすっかり味を占めた国で、プーチン氏はその第二次世界大戦当時と、ちっとも考えが変わっていない、武力侵攻による領土拡大の欲望を持つ人なのです。
トランプ大統領がよく「強いアメリカに」と言いますが、プーチン氏は違う意味で、武力的且つ領土拡大的な意味で、「強いロシアに」という言い方をし、当時に回帰しようとします。
■ プーチン氏「ウクライナ全土がロシアのもの」、スムイ州占領も示唆

ロシアのプーチン大統領は20日、ロシア人とウクライナ人は一つの民族であり、「その意味で、ウクライナ全体がわれわれのものだ」と主張した。
ロシアのプーチン大統領は20日、ロシア人とウクライナ人は一つの民族であり、「その意味で、ウクライナ全体がわれわれのものだ」と主張した。同時に、ロシアが戦線を拡大しているウクライナ北東部スムイ州を占領する可能性は排除しないとの見解を示した。
プーチン大統領は、サンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムで、ロシアがウクライナの主権を疑ったことは一度もないと言及。一方で、1991年にウクライナがソ連からの独立を宣言した際、それは「中立国」としてであったとの認識を示した。
プーチン氏は、ロシア軍はロシア領土を守るためスムイ州に緩衝地帯を設置しており、州都スムイを制圧する可能性も排除しないとの考えを表明。「ロシア兵が足を踏み入れた場所は、われわれのものだ」と領土拡張を巡る持論を展開した。
また、ウクライナが放射性物質を拡散する「汚い爆弾(ダーティーボム)」をロシアに対し使用すれば、ウクライナに壊滅的な影響がもたらされると警告。ただ、ウクライナがそうした計画を立てている証拠はまだ見られないとした。
プーチン氏は、ロシアはウクライナの降伏を求めているのではないとし、「ウクライナが戦場の現状を認識することを求めている」と述べた。
───── 以上、 ロイター 2025.6.21より
■ プーチン氏「ウクライナ全体は我々のもの」「兵士が足を踏み入れた場所はすべて我々のもの」
ロシアのプーチン大統領は20日、ロシア人とウクライナ人は「一つの民族」で、「その意味ではウクライナ全体は我々のものだ」と語り、ウクライナ侵略を改めて正当化した。露国境に位置するウクライナ北東部スムイ州の州都スムイの制圧を排除しない考えを明らかにし、支配地域の拡大を目指す意向を示した。
露西部サンクトペテルブルクで開かれた国際経済フォーラムの本会議で、司会者に露軍がどこまで侵攻するのかを問われ、答えた。
露軍は露西部への攻撃を防ぐ名目で「緩衝地帯」を作るとし、スムイ州内で実効支配する地域を拡大中だ。州都までは約20キロ・メートルに迫っているとされる。プーチン氏はスムイ制圧について「任務はないが、原則として排除しない」と言明した。「露軍兵士が足を踏み入れた場所は、すべて我々のものだ」とも強調し、露軍の支配下になった地域の放棄をウクライナ側に求めた。
これに対し、ウクライナのアンドリー・シビハ外相はSNSへの投稿で「米国の平和に向けた努力を完全に 軽蔑(けいべつ) した」と非難。「更なる占領と、より多くのウクライナ人の殺害を議論している」と反発した。
ウクライナは、ロシアがウクライナ南・東部4州などの併合を一方的に宣言したのは違法だと訴えているほか、ロシア人とウクライナ人が「一つの民族」との露側の主張も否定している。
ロシアとウクライナは5月と6月に2回、和平に向けた高官級協議を開いたが、露側が即時停戦を拒否し、成果は捕虜交換などにとどまっている。
───── 以上、 読売新聞デジタル 2025.6.21より
プーチン氏は、報道管制や、激しい言論弾圧、プロパガンダ等を使って、ウクライナ侵攻による本当の被害を国民にひた隠しにしている。国民は本当の被害を知るべきである。戦地に行ったまま連絡が取れない、父は夫は息子は、もう帰ってこないのだと知るべきである。
■ ロシア兵死傷者95万人 第2次大戦後で最多―ウクライナ侵攻
米シンクタンク、戦略国際問題研究所(CSIS)は3日、2022年2月に始まったウクライナ侵攻でロシア軍の兵士最大25万人が死亡したとの推計を発表した。軍事作戦に伴うロシア兵の死者としては、旧ソ連時代を含めて第2次大戦後最多。負傷者も加えた人的被害は95万人以上とみられる。
ウクライナ側の死者数は最大10万人。負傷者を含む人的被害は40万人に達している。
推計は英国防省が公表するデータなどに基づく。ロシア側の死者は年を追うごとに増えており、旧ソ連によるアフガニスタン侵攻(1979~89年)の1万5000人より圧倒的に多い。アフガン侵攻は国力の疲弊を招き、ソ連崩壊の一因になったとされる。
───── 以上、 時事通信 2025.6.4より
◆ガザ 繰り返される食糧支援の場での虐殺
ガザでは、国連の食糧支援が差し止められている。代わりに自分たちがやると言い出したGHF(米国とイスラエルが後押しする「ガザ人道財団(GHF)」)では、食糧を渡すどころか、虐殺を繰り返している。
ネタニアフ首相の本音は、ガザを軍事統治し、自分たちの入植地に変えることにある。入植地にするために、できればパレスチナ人はいない方がいいと思ってるから、虐殺をいとわない。
ハマスは無能だから、「イスラエル軍がガザから出て行くまで停戦に応じない」を、ただくり返す。だがネタニアフはガザから軍を引きあげる気なんてさらさらないから(先程の本音)、応じるはずがなく、結果、停戦は実現せず、戦闘(=虐殺)が延々引き延ばされるばかりである。
ネタニアフ政権を、イスラエル人の手によって更迭しないかぎり、ガザの虐殺は続く。平和は来ない。
■ 「ガザの命はこれほど軽いのか」 支援の場で撃たれた住民の怒り 6/1の話
「四方八方からイスラエル軍に銃撃された。戦車も砲弾を撃ち込んだ」――。パレスチナ自治区ガザ地区の支援物資の配布拠点付近で1日、230人以上の死傷者を出す惨事が起きた。現場で何があったのか。居合わせた人々の証言から、その一端が見えてきた。
ガザ地区南部ハンユニスのナセル病院。1日午前、毎日新聞の現地助手が駆けつけると、負傷者が次々と運び込まれていた。最南部ラファの配布拠点付近で発砲を受けた人々だった。
「午前5時ごろだった。突然、イスラエル軍が住民に向けて発砲を始めた。戦車も砲弾を撃ち込んだ」。ベッドに横たわり、顔に包帯を巻いたムハンマド・リズクさん(26)は、苦痛に顔をゆがめながら語った。
地面に伏せ、恐怖に震えながら銃声がやむのを待った。様子を見ようと頭を上げた人たちは撃たれて死亡したという。リズクさん自身も銃弾が頭部をかすめ、その場に倒れ込んだ。約1時間後にようやく救急車が到着した。
リズクさんは元々ラファに住んでいたが、現在はハンユニスで暮らす。兄弟がイスラエル軍の空爆で命を落とし、残された5人の子どもを代わりに育てている。自分にも3人の子どもがいて、食料の確保に日々苦心している。
この日も、わずかな望みにすがり、配布拠点まで約10キロ歩いて来たという。しかし、そこで目にしたのは、支援とはほど遠い光景だった。
リズクさんは「世界はなぜ虐殺を止めようとしないのか」と訴え、問いかけた。「国際社会の沈黙はなぜか。ガザ住民だって人間だ。そんなことすら分かってもらえないのか」
ガザでは、イスラエルが3月上旬から約2カ月半にわたって支援物資の配布を停止したため、深刻な食料危機に陥っている。国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、約200万人が暮らすガザの全住民が、何らかの食料不足に直面している。食料支援は、人々にとって文字通り「生命線」だ。
アフメド・モサビーフさん(29)は、中部デルバラーから約20キロ離れたラファを目指して歩き続けた。3日間ほとんど食事を取れず、口にできたのは水だけだったという。歩くのもやっとだったが、5人の子どもたちに食べ物を届けたい一心だった。
だが、たどり着いた先では、ドローン(無人機)などによるイスラエル軍の攻撃が待ち受けていた。「空からも、陸からも、海からも容赦なく撃たれた」と振り返った。
「配布拠点は、我々を救うためではなく、殺すために設けられたのだと悟った」。モサビーフさんは怒りを込めて言った。「支援は滞り、物価は暴騰し、人々の暮らしは限界だ。それなのに、ガザの命はこれほど軽いのか」
ガザ広報当局は1日、支援物資の配布拠点は「人道支援の場ではなく、多数の命を奪うためのわなだったことが証明された」と非難した。一方、イスラエル軍は配布拠点やその周辺での発砲を否定している。
この日、30人以上が死亡した配布拠点を運営していたのは、米国とイスラエルが後押しする「ガザ人道財団(GHF)」だった。5月下旬から国連に代わって支援を担っている。
だが、混乱は収まらず、死傷者が相次いでいる。ガザ当局によると、2日にもラファの配布拠点付近でイスラエル軍の攻撃により3人が死亡し、16人が負傷したという。
支援の名のもとに集まった人々が、再び犠牲になった。
───── 以上、 毎日新聞 2025.6.3より
■ 食料を待つパレスチナ人へ発砲を命令か、イスラエル軍は報道を否定 6/27の話

支援物資を取りに行こうとして死亡したパレスチナ人の葬儀を行う人たち=23日、パレスチナ自治区ガザ地区ガザ市
イスラエル国防軍(IDF)は、パレスチナ自治区ガザ地区で人道支援を待つ非武装のパレスチナ人に発砲するよう兵士が命令されたとする新たな報道を否定した。ここ数週間、食料配布所に近づいた市民が相次いで死亡しており、犠牲者は数百人に上っている。
イスラエルの有力紙ハアレツは27日、ガザに展開するイスラエル兵が、脅威がないことが明らかであったにもかかわらず、援助拠点に近づくパレスチナ人の群衆へ発砲するよう指揮官から命じられたと報じた。
同紙に匿名で証言した兵士は、援助拠点へ向かう経路を「殺戮(さつりく)の場」と表現し、そこでは差し迫った脅威がなくてもイスラエル軍が発砲すると語った。記事によれば、イスラエル軍は最近、群衆を解散させるため砲弾を使うようになり、そのため死傷者が急増したという。
IDFは報道を否定した。配給所に近づく市民を含め、民間人を意図的に攻撃するよう部隊に命じていないとし、民間人への意図的な攻撃を禁じていると説明した。
イスラエルのネタニヤフ首相とカッツ国防相も報道を一蹴し、世界で最も道徳的な軍であるIDFをおとしめる悪質なうそと断じた。
パレスチナ保健省によると、5月27日以降、援助拠点や支援物資を運ぶトラックに近づいたパレスチナ人が少なくとも500人以上死亡した。保健当局や救助隊員によれば、拠点に近づく市民がほぼ毎日銃撃を受けているという。
今月のある事案では、負傷者を含む十人以上の目撃者がCNNに対し、イスラエル兵が群衆に向けて一斉射撃を繰り返したと語った。武器の専門家は、映像の発砲音や被害者から回収された銃弾の画像がイスラエル軍の機関銃と一致すると指摘した。
IDFは、配給拠点付近の軍の陣地に接近するパレスチナ人に対して、複数の回の「警告射撃」を行ったことは認めている。死傷者に関する報告を調査しているとも明らかにしているものの、これまで調査結果を公表していない。
ハアレツ紙によれば、軍の法務総監は、戦争法違反の可能性がある事案を調査する軍の機関に対して、援助拠点周辺での戦争犯罪をめぐる疑惑を調査するよう指示した。
死者が出た援助拠点は、イスラエルと米国が主導する「ガザ人道財団(GHF)」が運営している。同財団はガザ南部と中部の数カ所で食料を配布しており、1カ月前の開始当初から混乱が続いている。拠点が開くと同時に群衆が殺到し、支援物資は1時間足らずでなくなることも多い。
GHFは、イスラエルと米国がイスラム組織ハマスによる支援物資の略奪を非難したことを受け、国連の支援機構に代わる形で設立された。ハマスは略奪をめぐる疑惑を否定しているほか、人道団体は国連の時の食料配布では大半は市民に届いていると指摘している。
───── 以上、 CNN 2025.6.29より
(島)